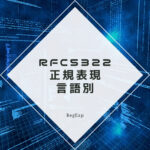「JSON-LD」「構造化データ」…言葉は聞いたことがあるけれど「なんだか難しそう…」
「SEOに重要とは分かっていても、何から手をつけていいか分からない…」
「エンジニアにどう依頼すればいいのか悩んでいる…」
もし、少しでもこう感じたことがあるなら、この記事はお役に立てます。
難しい専門用語を可能な限り使わず、JSON-LDの基本から具体的な書き方、そして実装後に失敗しないためのチェック方法まで、誰にでも分かるように徹底解説していきます。
この記事を読み終える頃には、JSON-LDを自信を持って使いこなし、Googleから正しく評価されるWebサイトを作るための、強力な武器を手にしているはずです。
さあ、一緒に検索結果のその先へ進みましょう。
そもそもJSON-LDとは?Webページの「分かりやすい名札」です
難しく考える必要はありません。
JSON-LDとは、あなたのWebページに「これは、こういう内容が書かれたページですよ」という分かりやすい名札(ラベル)をつけてあげるための記述方法の一つです。
人間はページを見れば、「これは会社の概要ページだな」「これは商品のレビュー記事だな」と瞬時に理解できます。
しかし、Googleなどの検索エンジン(クローラー)は、ただのプログラムです。
文章を100%正確に理解できるわけではありません。
そこでJSON-LDを使って、
- 「このページの運営組織名は〇〇です」
- 「この記事の著者は△△です」
- 「この商品の評価は星4.5です」
といった情報を、検索エンジンが理解できる言葉で伝えてあげる必要があります。
そして、「検索エンジンが理解できる言葉で書かれたデータ」を構造化データと呼びます。
JSON-LD・構造化データ・Schema.orgの関係性
この3つの関係性は、よく料理に例えられます。
- Schema.org(レシピ集):構造化データの「書き方のルール」を定めている国際的なコミュニティです。「会社情報を書くときは、この項目を使いなさい」「レシピを書くときは、この材料を書きなさい」といったルール(ボキャブラリー)がまとめられています。
- JSON-LD(調理方法): レシピ集(Schema.org)に載っている料理を作るための、調理方法の一つです。他にもMicrodata(マイクロデータ)などの調理方法がありますが、JSON-LDが最もGoogleに推奨されている、現代の主流な調理方法です。
- 構造化データ(完成した料理):レシピ集(Schema.org)のルールに従い、JSON-LDという調理方法で作られた、検索エンジン向けのデータそのものです。
つまり、「Schema.orgというレシピ集を見て、JSON-LDという調理方法で、構造化データという料理を作る」とイメージすれば完璧です。
なぜJSON-LDがSEOに必須なのか?検索順位を押し上げる3つの重要なメリット
JSON-LDを実装すると、SEOにおいて非常に強力なメリットがあります。
1. 検索結果がリッチになる(リッチリザルト)
近年の検索結果画面で、通常のタイトルや説明文だけでなく、星評価、価格、FAQ、イベント日などが表示されているのを見たことはありませんか?
あれがリッチリザルトです。
JSON-LDを正しく実装することで、このような特別な表示がされる可能性が高まり、検索結果画面での視認性が格段に向上し、クリック率(CTR)の大幅な改善が期待できます。
2. Googleのページ理解を助け、間接的に評価を高める
JSON-LDは、Googleにページの内容を正確に伝える「公式カンニングペーパー」のようなものです。
Googleがあなたのページを正しく理解できれば、「このページは、このキーワードに対して非常に専門性が高い情報を提供している」と判断されやすくなります。
これは、Googleが重要視するE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の評価にも間接的によい影響を与えます。
3. 音声検索やAI検索への対応
「OK Google, 〇〇のレシピを教えて」といった音声検索や、今後のAIによる検索において、構造化されたデータはますます重要になります。
JSON-LDを実装しておくことは、未来の検索エンジンへの最適化、いわば未来へのSEO対策とも言えます。
【多角的な比較表】Microdataはもう古い?GoogleがJSON-LDを推奨する理由
以前はMicrodata(マイクロデータ)という記述方法も使われていました。
しかし現在、GoogleはJSON-LDを明確に推奨しています。
その違いは一目瞭然です。
| 比較項目 | JSON-LD(推奨) | Microdata(旧式) |
|---|---|---|
| 記述場所 | <script>内にまとめて記述可能 | HTMLタグの中に一つ一つ属性を埋め込む |
| 管理のしやすさ | 非常に楽。HTML本体と分離されているため、修正や追加が簡単。 | 非常に大変。HTML構造が複雑になり、修正箇所を探すのが困難。 |
| 実装の難易度 | 比較的簡単。コピペで実装しやすい。 | HTMLの深い知識が必要で、ミスが起こりやすい。 |
| Googleの推奨度 | ◎(強く推奨) | △(サポートはされているが非推奨) |
| 結論 | 迷わずJSON-LDを選ぶべき | よほどの理由がない限り、新規での利用は避けるべき |
このように、JSON-LDは「管理がしやすく、ミスが起きにくい」という点で、Webサイト運営者にとって実は非常に優れた方式なのです。
目的別!すぐに使えるJSON-LD実装テンプレート集
お待たせしました!ここからは、あなたのサイトですぐに使えるJSON-LDのテンプレートをご紹介します。
まずは以下の3つを実装するだけでも、サイトの評価は大きく変わります。
まずはこれだけ!全サイト共通の「組織情報」と「パンくずリスト」
① 組織情報(Organization)
あなたの会社やサイト運営者の情報をGoogleに伝えます。トップページに実装しましょう。
<script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Organization",
"name": "あなたの組織名またはサイト名",
"url": "https://あなたのサイトURL.com/",
"logo": "https://あなたのサイトURL.com/logo.png",
"sameAs": [
"https://twitter.com/your_account",
"https://www.facebook.com/your_account"
]
}
</script>
name,url,logoはご自身の情報に書き換えてください。sameAsには、関連するSNSアカウントのURLを記載します。
② パンくずリスト(BreadcrumbList)
ユーザーがサイトのどこにいるかを示すパンくずリストを構造化データで伝えます。
これはクリック率向上にも繋がる重要な設定です。
<script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "BreadcrumbList",
"itemListElement": [{
"@type": "ListItem",
"position": 1,
"name": "トップページ",
"item": "https://あなたのサイトURL.com/"
},{
"@type": "ListItem",
"position": 2,
"name": "カテゴリ名",
"item": "https://あなたのサイトURL.com/category/"
},{
"@type": "ListItem",
"position": 3,
"name": "現在のページ名",
"item": "https://あなたのサイトURL.com/category/current-page/"
}]
}
</script>
positionの番号と各name, item(URL)を、ご自身のサイト構造に合わせて書き換えてください。
ブログ記事の評価を最大化する「Article」スキーマの書き方
ブログ記事やニュース記事のページには、この記事が「いつ、誰が書いた、どんな内容の記事か」を伝えるArticleスキーマを実装しましょう。
<script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Article",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "記事のURL"
},
"headline": "記事のタイトル",
"image": ["記事のメイン画像のURL"],
"datePublished": "2025-09-27T08:00:00+09:00",
"dateModified": "2025-09-27T09:20:00+09:00",
"author": {
"@type": "Person",
"name": "著者名"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "あなたの組織名またはサイト名",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "https://あなたのサイトURL.com/logo.png"
}
}
}
</script>
datePublished(公開日)と dateModified(更新日)は、ISO 8601形式(YYYY-MM-DDThh:mm:ss+09:00)で記述します。+09:00は日本時間を示します。
ユーザーの疑問に答えてクリック率を上げる「FAQ」スキーマの書き方
「よくある質問」とその回答をまとめたページに実装すると、検索結果上で質問と回答がアコーディオン形式で表示されることがあります。
これは非常に目立ち、クリック率を大幅に向上させる効果が期待できます。
<script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "FAQPage",
"mainEntity": [{
"@type": "Question",
"name": "一つ目の質問をここに書きます",
"acceptedAnswer": {
"@type": "Answer",
"text": "一つ目の質問に対する回答をここに書きます。"
}
}, {
"@type": "Question",
"name": "二つ目の質問をここに書きます",
"acceptedAnswer": {
"@type": "Answer",
"text": "二つ目の質問に対する回答をここに書きます。"
}
}]
}
</script>
質問と回答のセット{...}は、カンマ,で区切って必要な数だけ追加できます。
【超重要】JSON-LDはHTMLのどこに書くのが正解?設置場所を解説
Googleはどちらでも認識しますが、一般的にはタグ内に記述することが推奨されています。
ページのコンテンツとは別に、メタ情報としてまとめて管理できるためです。
失敗から学ぶ!JSON-LD実装で初心者がハマる5つの罠と解決策
JSON-LDは非常に強力ですが、たった一文字の間違いで全く機能しなくなってしまう繊細なものでもあります。
ここでは、「実務者が実際に経験した失敗談」と、皆さんが同じ轍を踏まないための解決策を紹介します。
【ある実務者の失敗談】たった1つのカンマ忘れでリッチリザルトが消えた話
これは、ある実務者がまだマーケターとして駆け出しだった頃の話です。
ある重要なページのFAQスキーマを修正していた際、複数の質問を繋ぐカンマ(,)を一つだけ消し忘れてしまいました。
「まあ、これくらい大丈夫だろう」と高を括っていたその実務者は、数日後に愕然としました。
それまで表示されていたFAQのリッチリザルトが、検索結果から綺麗さっぱり消えていたのです。
原因はそのたった一つのカンマでした。ツールでエラーを特定して修正するまでに、丸一日近くを無駄にしてしまったといいます。
JSON-LDは、「カンマ(,)や引用符(")、括弧({})の閉じ忘れといった、ほんの些細な構文エラー」で、データ全体が無効になってしまいます。
構文エラーをゼロに!実装前に必ず確認したい【診断チェックリスト】
上記の私の失敗談のようにならないために、実装前には必ず以下の項目を指差し確認してください。
- すべての文字列はダブルクォーテーション
"で囲まれていますか?('ではない) - 項目の終わりにはカンマ
,が正しく打たれていますか?(最後の項目には不要) - 開始の括弧
{や[と、終了の括弧}や]の数は合っていますか? - 日付は
YYYY-MM-DDThh:mm:ss+09:00の形式になっていますか? - Schema.orgで定義されたプロパティ名(例: headline)をタイポしていませんか?
Google公式ツールで答え合わせ!「リッチリザルトテスト」の使い方
実装前、そして実装後には、必ずGoogleが無料で提供している公式ツールでテストを行いましょう。
使い方は簡単です。
- テストしたいページのURLを入力するか、直接コードを貼り付けます。
- 「URLをテスト」または「コードをテスト」ボタンをクリックします。
- 数秒待つと、Googleがそのページの構造化データをどのように認識しているかが表示されます。
「ページはリッチリザルトに対応しています」と緑色のチェックマークが出れば成功です。
もしエラー(赤色)や警告(黄色)が出た場合は、どの部分に問題があるのかを具体的に教えてくれるので、指示に従って修正しましょう。
【具体的なケーススタディ】JSON-LDを実装すると検索結果はこう変わる!
言葉で説明するよりも、実際の例を見るのが一番です。
JSON-LDを実装することで、あなたのサイトの検索結果は魅力的になります。
事例で見る!「FAQ」や「レビュー」で検索結果がリッチになる様子
【実装前:通常の検索結果】
〇〇の使い方を徹底解説|株式会社サンプル
[https://sample.com/how-to-use](https://www.google.com/search?q=https://sample.com/how-to-use)
〇〇の基本的な使い方から、応用テクニックまでを網羅的に解説します。初心者の方でも安心してご利用いただけるよう...
【実装後:FAQリッチリザルトが表示された検索結果】
〇〇の使い方を徹底解説|株式会社サンプル
[https://sample.com/how-to-use](https://www.google.com/search?q=https://sample.com/how-to-use)
〇〇の基本的な使い方から、応用テクニックまでを網羅的に解説します。初心者の方でも安心してご利用いただけるよう...
よくある質問
▼ 〇〇の料金はいくらですか?
▼ 〇〇の対応OSは何ですか?
▼ 〇〇の解約方法は?
どちらがクリックしたくなるかは、一目瞭然ですよね。
これがJSON-LDの力です。
もう迷わない!JSON-LDに関する「よくある質問(FAQ)」
最後に、読者の皆さんからよくいただく質問とその回答をまとめました。
Q. WordPressを使っています。プラグインで簡単に実装できますか?
A. はい、可能です。
高品質なSEOプラグイン(例えば「Yoast SEO」や「Rank Math」など)には、JSON-LDを自動で出力してくれる機能が備わっています。
記事の公開日や組織情報などを自動で設定してくれるため、非常に便利です。
ただし、FAQなど特定のコンテンツに対応させるには、手動での追加や専用ブロックの使用が必要になる場合があります。
Q. JSON-LDを実装すれば、必ずリッチリザルトに表示されますか?
A. いいえ、必ず表示されるとは限りません。
JSON-LDは、あくまでGoogleにリッチリザルトの候補として情報を提案するものです。
最終的に表示するかどうかは、検索キーワードやユーザーの状況、サイトの品質など、様々な要因をGoogleが総合的に判断して決定します。
ただし、実装しなければ表示される可能性はゼロなので、正しく実装しておくことが非常に重要です。
Q. 1つのページに複数のJSON-LDを記述しても問題ありませんか?
A. 問題ありません。むしろ推奨されています。
例えば、一つの記事ページに「Article」スキーマと「BreadcrumbList」スキーマ、そして「FAQPage」スキーマが同居することは全く問題ありません。
まとめ|JSON-LDを使いこなし、Googleとユーザーに愛されるサイトへ
今回は、SEO効果を最大化するためのJSON-LDについて、基本から実践までを徹底的に解説しました。
最後に、今日の重要なポイントを振り返りましょう。
- JSON-LDは、Webページに付ける「分かりやすい名札」
- Googleにページ内容を正しく伝え、リッチリザルト表示を狙うために必須
- 実装は推奨されている内に、コピペでOK
- カンマや引用符などの些細なミスに注意
- 実装後は必ず「リッチリザルトテスト」で確認する
最初は少し難しく感じるかもしれませんが、一度理解してしまえば、JSON-LDはあなたのサイトにとって最強の武器になります。
さあ、まずはこの記事で紹介した「組織情報」のテンプレートをコピーし、あなたのサイトのトップページにすることから始めてみませんか?
小さな一歩が、未来の大きな成果へと繋がっています。